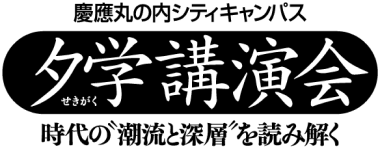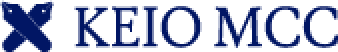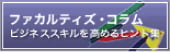講師紹介
このページを印刷

講演日 2025/06/10 (火)
落合 陽一
オチアイ ヨウイチ
メディアアーティスト
講師略歴
1987年生まれ、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了(学際情報学府初の早期修了)、博士(学際情報学)。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、准教授・JSTCRESTxDiversityプロジェクト研究代表。IPA認定スーパークリエータ/天才プログラマー。2017年〜2019年まで筑波大学学長補佐、2018年より内閣府知的財産戦略ビジョン専門調査会委員、内閣府「ムーンショット型研究開発制度」ビジョナリー会議委員、デジタル改革法案WG構成員、文化庁文化交流使、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーなどを歴任。Prix Ars Electronica、SXSW Arrow Awards、MIT Innovators Under 35 Japanなど受賞多数。写真家・随筆家など、既存の研究や芸術活動の枠を自由に越境し、探求と表現を継続している。近年の展示として「おさなごころを、きみに」東京都現代美術館 2020、「Ars Electronica」オーストリア 2021、「晴れときどきライカ」ライカギャラリー東京•京都 2023、「ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」山梨・光の美術館 2023など多数。Yoichi Ochiai Official Website:https://yoichiochiai.com/
Official YouTube「落合陽一の現場録」:https://www.youtube.com/@ochyai_gemba
落合陽一公式note:note.com/ochyai
落合陽一塾(オンラインサロン):lounge.dmm.com/detail/48
落合陽一公式X(旧Twitter):@ochyai
写真:©蜷川実花
講演内容
【ハイブリッド受講】メディア芸術と計算機自然
本講演では、メディア芸術と計算機自然(デジタルネイチャー)の概念を通じ、テクノロジーが人間の知覚・文化・社会をいかに再構築するかを探求します。これまでの研究・作品を例に、新しい自然観と創造的表現、そして社会実装の可能性を考察し、未来の芸術と社会の姿を展望します。※本講演は、講演60分・質疑応答30分(20:00終了)の構成です
◎見逃し配信日程 ※本講演を予約された方のみ
2025年6月20日(金)0:00 ~ 6月26日(木)23:59
視聴方法は受講券を購入された方のご登録メールアドレス宛に、見逃し配信開始日の2営業日前にメールでご案内します。
主要著書
『「好き」を一生の「強み」に変える育て方』(共著)、サンマーク出版、2025年『猫でもわかる生成AI 落合陽一に100のプロンプトを入力してみた』扶桑社、2025年
『2035年の人間の条件』(共著)、マガジンハウス (マガジンハウス新書)、2024年
『落合陽一責任編集 生成AIが変える未来 加速するデジタルネイチャー革命』扶桑社(扶桑社ムック)、2024年
『晴れときどきライカ』 文藝春秋、2023年
『xDiversityという可能性の挑戦』(共著)、講談社、2023年
『予言された世界』(共著)、 小学館、2022年
『忘れる読書』 PHP研究所(PHP新書)、2022年
『ズームバック×オチアイ 過去を「巨視」して未来を考える』NHK出版、2022年
『落合陽一 34歳、「老い」と向き合う:超高齢社会における新しい成長』中央法規出版、2021年
『半歩先を読む思考法』新潮社、2021年
『働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ』 小学館(小学館新書)、2020年
『2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望』SBクリエイティブ、2019年
『0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる 学ぶ人と育てる人のための教科書』小学館、2018年
『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』PLANETS/第二次惑星開発委員会、2018年
『ニッポン2021-2050 データから構想を生み出す教養と思考法』(共著)、KADOKAWA、2018年
『10年後の仕事図鑑』(共著)、SBクリエイティブ 、2018年
『日本再興戦略』幻冬舎、2018年
『超AI時代の生存戦略 シンギュラリティ<2040年代>に備える34のリスト』大和書房、2017年
『これからの世界をつくる仲間たちへ』小学館、2016年
『魔法の世紀』Planets、2015年
『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(共著)、河出書房新社、2014年
このページを印刷