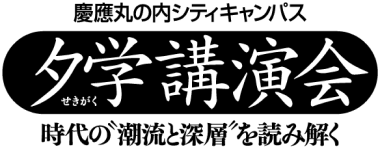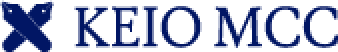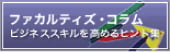講師紹介
このページを印刷

講演日 2018/07/06 (金)
白井 さゆり
シライ サユリ
慶應義塾大学総合政策学部 教授
講師略歴
1993年 コロンビア大学大学院・経済学研究科博士課程修了 経済学博士(Ph.D)1993年 国際通貨基金(IMF)エコノミスト
1998年 慶應義塾大学総合政策学部 助教授
2006年 慶應義塾大学総合政策学部 教授
2007年 フランス、パリ政治学院 客員教授(~2008年まで)
2011年 4月 日本銀行 政策委員会 審議委員(~2016年3月まで)
2016年 4月 慶應義塾大学総合政策学部 特別招聘教授
2016年 4月 アジア開発銀行研究所 客員研究員(現在も兼任)
2016年 9月 慶應義塾大学総合政策学部 教授
日本を含む世界経済や金融政策について配信(2017年12月~2018年5月まで)
小学館BOOK PEOPLE「岐路に立つ日本経済」: http://bp.shogakukan.co.jp/crossroads/
ホームページのURL: http://www.sayurishirai.jp/
TV東京「モーニングサテライト」、ブルームバーグTVとCNBC(いずれも海外英語放送)、NHKマイあさラジオ「社会の視点・私の見方」にレギュラーコメンテーターとして出演。そのほか、複数の日本のテレビ番組、NHK World、英国BBCのTV番組、シンガポールのChannel AsiaのTV番組、中国のCCTVなどにでも、日本経済、世界経済、金融政策等についてインタビューまたはコメンテーターとして出演。ジャパンタイムズ紙やウオール・ストリート・ジャーナル紙にも数多くの論説を執筆。世界の中銀の金融政策や経済記事を扱う英国のWeb雑誌『Central Banking』にも日銀等の金融政策について論文を執筆。週刊エコノミストの書評を担当。食品関連企業の社外取締役も兼任。ほぼ毎月、欧州、米国、アジア等の海外の国際会議や講演会等に出席し、数多くの講演や投資家との懇談会を実施。
講演内容
「東京五輪後の日本経済」中央銀行は、象牙の塔から抜け出しもっと国民と向き合うべきです。これまでの中銀は、専門性や抽象度が高いことから、国民生活に直結しているのに国民の関心が集まることはありませんでした。中銀の対話の相手は市場参加者や金融専門のメディアが中心で、難解な用語を使って曖昧な説明に終始しても問題視されることもなかったのです。
その状況が一変するのが、日銀が2013年4月に異次元緩和を導入してからです。2年で2%の物価安定目標を掲げて総裁に就任した黒田東彦氏のもとで、それを実現すべく長期国債や株式投信・不動産投信をめいっぱい買い入れました。その結果、長期金利は低下し超円高や株安は払拭され、企業の収益改善や株式・不動産市場の活性化に寄与しましたが、足許のインフレ率は2%目標からはほど遠く、市場価格に歪みをもたらす国債と株式の大量買い入れに市場参加者は漠然とした不安を抱えています。
現在の日本経済は、世界景気の回復基調とオリンピック特需と異次元緩和による円安誘導に支えられ順調な景気拡大局面にありますが、それらの要因が剥落すれば本来の(より低い)成長力に戻っていきます。そのとき慌てるのでははく、日本経済の行く末について率直に国民と向き合って、今から対応を考えておく必要があります。アベノミクスの成果も大きいですが、取り組めていない政策も多いのです。正しく現状をみつめ今後の日本をどうしたいのか国民一人一人が向き合う時期にあるからこそ、私の経験と分析をもとに日本経済の先行きについてお話ししたいと思います。
主要著書
『検証 IMF経済政策-東アジア危機をこえて』東洋経済新報社、1999年『カレンシーボードの経済学-香港にみるドル連動性の再考』日本評論社、2000年
『入門 現代の国際金融』東洋経済新報社、2002年
『メガバンク危機とIMF経済政策』角川書店、2002年
『人民元と中国経済』日本経済新聞社、2004年
『マクロ開発経済学-対外援助の新潮流』有斐閣、2005年
『これならわかる日本の実力-国際比較くらしと経済』NHK出版、2007年
『欧州迷走-揺れるEU経済と日本・アジアへの影響』日本経済新聞出版社、2009年
『欧州激震-経済危機はどこまで拡がるのか-』日本経済新聞出版社、2010年
『ユーロ・リスク』日本経済新聞出版社、2011年
『超金融緩和からの脱却』日本経済新聞社、2016年
『Mission Incomplete: Reflating Japan’s Economy』Asian Development Bank Institute、2017年
※ホームページより無料ダウンロードできます。
『東京五輪後の日本経済』小学館、2017年
このページを印刷