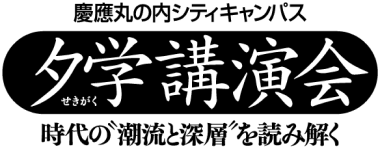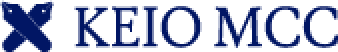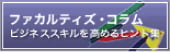講師紹介
このページを印刷

講演日 2016/12/02 (金)
池尾 和人
イケオ カズヒト
慶應義塾大学経済学部 教授
講師略歴
1953年 京都生まれ1975年 京都大学経済学部卒業
1980年 一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
1980年 岡山大学経済学部助手
1986年 京都大学経済学部助教授
1987年 京都大学経済学博士(論文『日本の金融市場と組織』による)
1984年 慶應義塾大学経済学部助教授
1995年 同 教授(現在に至る)
講演内容
「異次元緩和と財政ファイナンス」量的・質的金融緩和政策は、2年程度で決着を付けて手仕舞いすることを想定した「短期決戦型」の立て付けのものである。ところが、その意図は実現できず、なし崩し的に長期戦を戦うことに追い込まれて、困難に直面している。金融政策の立て付けそのものを見直すことが望まれているが、「失敗」を認めることになるそうした見直しはなされ得ずにいる。しかし、ずるずると現状を続けていると、金融緩和のはずが財政ファイナンスに変質していくことが懸念される。歴史的にみたとき、インフレ(とくに大インフレ)は財政的現象であることを想起しなければならない。
主要著書
『コモディティ市場と投資戦略』(大野早苗と共編)勁草書房、2014年『連続講義・デフレと経済政策』日経BP社、2013年
『金融依存の経済はどこへ向かうのか―米欧金融危機の教訓』(編著)、日本経済出版社、2013年
『現代の金融入門(新版)』筑摩書房(ちくま新書)、2010年
『なぜ世界は不況に陥ったのか』(池田信夫との共著)、日経BP社、2009年
『バブル/デフレ期の日本経済と経済政策4 不良債権と金融危機』(編著)、慶應義塾大学出版会、2009年
『開発主義の暴走と保身 金融システムと平成経済』NTT出版(日本の<現代>7)、2006年
『市場型間接金融の経済分析』(財務省財務政策総合研究所と共編)、日本評論社、2006年
『日本の産業システム9 金融サービス』(堀内昭義と共編)、NTT出版、2004年
『エコノミクス 入門 金融論』(編著)、ダイヤモンド社、2004年
『銀行はなぜ変われないのか』中央公論新社、2003年
『日韓経済システムの比較制度分析』(黄圭燦・飯島高雄との共著)、日本経済新聞社、2001年
『現代の金融入門』筑摩書房、1996年
『金融産業への警告』東洋経済新報社、1995年
『ゼミナール 現代の銀行』(金子隆・鹿野嘉昭と共著)、東洋経済新報社、1993年
『金融理論と制度改革』(貝塚啓明との共編)、有斐閣、1992年
『銀行リスクと規制の経済学』東洋経済新報社、1990年
『日本の金融市場と組織』東洋経済新報社、1985年
このページを印刷