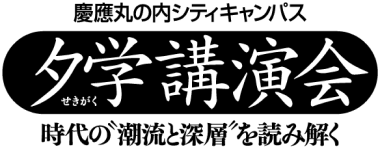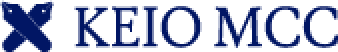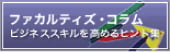講師紹介
このページを印刷
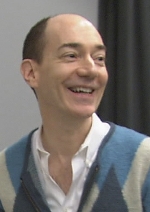
講演日 2010/01/15 (金)
ロバート・キャンベル
_
東京大学大学院総合文化研究科 教授
講師略歴
1957年 米国ニューヨーク市生まれハーバード大学大学院卒(Ph.D)
九州大学文学部専任講師(国語国文学)、国文学研究資料館助教授を経て
2000年 東京大学大学院総合文化研究科助教授
2007年 同研究科教授
近世~明治時代の日本文学を専攻
所属学会
日本近世文学会、日本近代文学会、俳文学会、AAS (Association for Asian Studies)
講演内容
「日本の近代 始めにあって今はなきものとは」世界史をひもとくと19世紀前半は欧米列強の独壇場である。しかし後半の50年を見ると、東アジア、
東欧、中近東において脱(反)植民地運動が起こり、国家統合という大きなうねりが盛り上がってくる。
交通手段と通信技術の発達が進み、世界がはじめて「一つ」になるのも同時期だ。明治維新も、「国史」
として理解されることが多いが、世界規模の流れと無関係に行われたわけではない。この講義では、
維新前後の日本人が世界をどのように捉えようとしたかを検証しながら、現代の日本社会についても、
考えてみたいと思っている。
主要著書
『新日本古典文学大系明治編―海外見聞集』(共著)、岩波書店、2009年『江戸の声―黒木文庫でみる音楽と演劇の世界』(編著)、東京大学出版会、2006年
『明治漢文小説集』(共著)、岩波書店、2005年
『パリ1900年・日本人留学生の交遊―『パンテオン会雑誌』資料と研究』(責任編集〔共編〕)、ブリュッケ、
2004年
『読むことの力―東大駒場連続講義』(編著)、講談社(講談社選書メチエ)、2004年
このページを印刷