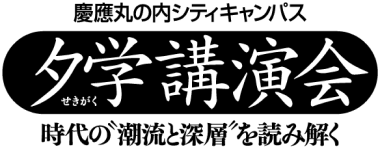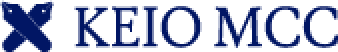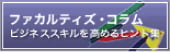講師紹介
このページを印刷

講演日 2004/11/16 (火)
山内 昌之
ヤマウチ マサユキ
東京大学大学院総合文化研究科 教授
講師略歴
1947年 札幌生まれ1971年 北海道大学文学部卒業後、カイロ大学客員助教授、東京大学教養学部助教授、
トルコ歴史協会研究員、ハーバード大学客員研究員などを経て
1993年~ 現職
学術博士(東京大学)
専攻 国際関係史、イスラーム地域研究
小泉首相の外交を補佐する「対外関係タスクフォース」の委員の他に、日本アラブ対話フォーラム、
日加フォーラム、「日韓歴史共同研究推進計画」合同支援委員会、外務省イスラム研究会、経済産業省
資源調査会、経団連フォーラム21アカデミック・アドヴァイザーの各委員なども務めている
2003年9月から10月には第1回政府中東文化ミッション団長として中東4ケ国を訪問、今年9月にも第2回
ミッション団長として中東2ケ国、10月にはトルコと中央アジア2ケ国に文化ミッションを組織して出張予定
講演内容
「歴史から考える日本と欧米とイスラーム~福沢諭吉から現代まで~」鎖国が解けた直後の文久2(1862)年に、徳川幕府は最初の公式遣欧使節団を送った。その一行のなか
に福沢諭吉がいた。福沢は『西航記』『西航手帳』などでヨーロッパや中東イスラーム世界での見聞を記録
している。福沢やほかの幕府直参らの目に中東やイスラームの政治や風俗はどう映ったのであろうか。
かれらの観察などを紹介しながら、近代日本と欧米との狭間にあった中東イスラーム世界の歴史的現実を
考える。これによって、21世紀における日本・欧米・イスラームの文明間対話を考えるよりどころを得てみたい。
主要著書
『現代のイスラム』朝日新聞社、1983年(発展途上国研究奨励賞)『スルタンガリエフの夢』東京大学出版会、1986年(サントリー学芸賞)
『瀕死のリヴァイアサン』TBSブリタニカ、1990年(毎日出版文化賞)
『ラディカル・ヒストリー』中央公論新社、1991年(吉野作造賞)
『イスラムとアメリカ』岩波書店、1995年
『イスラムとロシア』東京大学出版会、1995年
『世界の歴史(20)-近代イスラームの挑戦』中央公論新社、1996年
『帝国の終末論』新潮社、1996年
『納得しなかった男』岩波書店、1999年(司馬遼太郎賞)
『岩波イスラーム辞典』(共編著)、岩波書店、2002年(毎日出版文化賞)
『歴史の作法』文藝春秋(文春新書)、2003年
『帝国と国民』岩波書店、2004年
『歴史のなかのイラク戦争』NTT出版、2004年
編集委員として『岩波講座 世界歴史』『岩波講座 開発と文化』(岩波書店)、『世界の歴史』(中央公論新社)
などの企画と刊行にもあたる
■講師著書一覧
このページを印刷